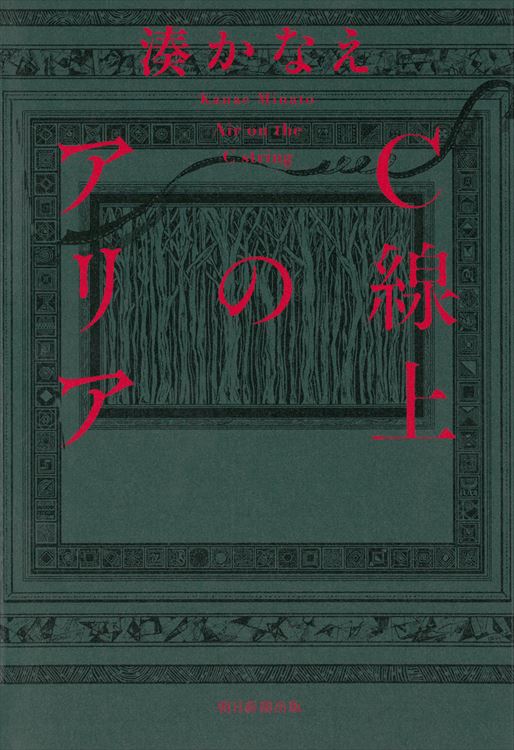【第307回】間室道子の本棚『C線上のアリア』湊かなえ/朝日新聞出版
「元祖カリスマ書店員」として知られ、雑誌やTVなどさまざまなメディアで本をおススメする、代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ・間室道子。
本連載では、当店きっての人気コンシェルジュである彼女の、頭の中にある"本棚"を覗きます。
本人のコメントと共にお楽しみください。
* * * * * * * *
『C線上のアリア』
湊かなえ/朝日新聞出版
※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。
※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。
* * * * * * * *
劇作のテクニック・ルールに「チェーホフの銃」というのがある。「もし第一幕に銃を出したら、二幕か三幕でそれが発砲されねばならない。そうでないならそもそも一幕に盛り込んではならない」。
たしかに、お芝居の初めに「館の壁には弾が装填されたままのライフルが掛けてあった」と出て、「じつはこれ、なんでもありませんでした」で幕が下りたら観客たちは、だはだは、となるだろう。
一方ミステリーには「レッド・へリング=赤いニシン」という手法がある。作者が真相から読者の注意をそらすためあちこちに仕込むもの。たとえば「その家の廊下には青汁やらボトル焼酎やらの段ボール箱が置かれていて、家族の誰もが蹴つまづく」という文章があったとしよう。
舞台上の猟銃に比べ、小説内の青汁は、「次の章で誰かが足をぶつけてすっ転んで死ぬ」にならなくてもいいだろう。箱買い商品を廊下置きって日本のご家庭あるあるだもの。で、段ボールはただの描写かもしれないし、のちに誰かが転倒死するきっかけかもしれない。ミステリーファンは「銃か、ニシンか」を見極めながらページをめくる。推理小説の醍醐味だ。
前置きが長くなったが、湊先生の『C線上のアリア』は、赤いニシンの使われ方がばつぐんにうまい。選び抜かれたアイテムやせりふ。そう、ニシンは置かれるならうさん臭さプンプンではなく、銀の輝きで読み手を食いつかせねばならない。
主人公は中年の主婦・美佐。彼女は列車で叔母・弥生さんの家に向かっている。両親を事故で失ったあとの高校の三年間、美佐は山間の町にある「みどり屋敷」で、旦那さんを早くに亡くした弥生さんとふたり暮らしをしていたのだ。訪れるのは結婚以来二十数年ぶり。今回いろんなものを振りきって遠出をしてきたのは、山の町役場からの電話のためだった。「不衛生な服装」「異臭」・・・。
丁寧な暮らしに満ちていたそこはゴミ屋敷と化しており、庭にいた弥生さんはあきらかに認知症を発症していた。でも今はまだ過去と現在がまだらのようだ。役場の助けで叔母さんをよい施設に入れることができた美佐は屋敷の片づけを始める。さあ、ここからだ。
ゴミ袋の中から出てきた現金、大量にため込まれた「命の水」のペットボトル、堆肥製作のバイオチップ、切れたままの電球、昔の状態を保っていた叔母の部屋にあったものとその中から出てきたもの、階段の上からの「うわっ」という声、表情の見えない若い男、それにしてもぜんぜん連絡をよこさない美佐の夫、ボン・ジョビ、ビートルズ、そしてアノ作家の大ベストセラー!
主人公を含めた登場人物たちの言葉も意味深だ。「人間一人の処分代なんて、一〇〇〇円あれば充分なのね」「こんなところに、あんな人がいるんだ」「夫は・・・森へ行ってるんです」「エルメスはどこにやった!」「あんたたち、おかしなことをたくらんでるなら、やめときな」
どれがなんでもないものでどれが物語の真実に迫る鍵か。鍵だったとして、それは「見た目どおり」なのか。絶妙さは湊かなえ先生ならでは。
本書で描かれるのは、人生で一番つらく当たられた人の世話を一手に引き受けていて、しかもまったく感謝されない人たち。その名は、主婦。
悩ましいのは、自由になる手段があり、ノーというべき時が来ても、彼女たちは無用になったものや苦しみを後生大事に抱え込み手放さない。なぜなら、「じゃあ今までのがんばりは何だったのか」と己の積み上げた時間を否定することになるからだ。憎い相手以上に、自分自身への敗北宣言――それは出来ない。登場する女たちが、弱くてみじめでよよよ、と泣くタイプではなく、負けず嫌いぞろいであるのが読みどころ。
そして湊先生の「ヨメ姑もの」(!)でよくあるように、本書でも男たちはある意味アッパレなくらい、ほーんとなんにもしない。ある一つを除いては。
というわけで巷にあふれる鬼の姑、地獄の家庭生活的作品とは一線を画す。義母からのねちねちした嫌味をねちねち描かれたら不快で本をブン投げたくなるが、湊先生は場面や状況を短文で活写する。だから読み味としてはキレよく突き抜けた感じで、言われた側のやるせなさ、くやしさは存分に伝わる。もうサイコー。
上と下、赤と緑、過去と今、他人の家と我が家が複雑に絡み合う、あらたなる湊マジック!
たしかに、お芝居の初めに「館の壁には弾が装填されたままのライフルが掛けてあった」と出て、「じつはこれ、なんでもありませんでした」で幕が下りたら観客たちは、だはだは、となるだろう。
一方ミステリーには「レッド・へリング=赤いニシン」という手法がある。作者が真相から読者の注意をそらすためあちこちに仕込むもの。たとえば「その家の廊下には青汁やらボトル焼酎やらの段ボール箱が置かれていて、家族の誰もが蹴つまづく」という文章があったとしよう。
舞台上の猟銃に比べ、小説内の青汁は、「次の章で誰かが足をぶつけてすっ転んで死ぬ」にならなくてもいいだろう。箱買い商品を廊下置きって日本のご家庭あるあるだもの。で、段ボールはただの描写かもしれないし、のちに誰かが転倒死するきっかけかもしれない。ミステリーファンは「銃か、ニシンか」を見極めながらページをめくる。推理小説の醍醐味だ。
前置きが長くなったが、湊先生の『C線上のアリア』は、赤いニシンの使われ方がばつぐんにうまい。選び抜かれたアイテムやせりふ。そう、ニシンは置かれるならうさん臭さプンプンではなく、銀の輝きで読み手を食いつかせねばならない。
主人公は中年の主婦・美佐。彼女は列車で叔母・弥生さんの家に向かっている。両親を事故で失ったあとの高校の三年間、美佐は山間の町にある「みどり屋敷」で、旦那さんを早くに亡くした弥生さんとふたり暮らしをしていたのだ。訪れるのは結婚以来二十数年ぶり。今回いろんなものを振りきって遠出をしてきたのは、山の町役場からの電話のためだった。「不衛生な服装」「異臭」・・・。
丁寧な暮らしに満ちていたそこはゴミ屋敷と化しており、庭にいた弥生さんはあきらかに認知症を発症していた。でも今はまだ過去と現在がまだらのようだ。役場の助けで叔母さんをよい施設に入れることができた美佐は屋敷の片づけを始める。さあ、ここからだ。
ゴミ袋の中から出てきた現金、大量にため込まれた「命の水」のペットボトル、堆肥製作のバイオチップ、切れたままの電球、昔の状態を保っていた叔母の部屋にあったものとその中から出てきたもの、階段の上からの「うわっ」という声、表情の見えない若い男、それにしてもぜんぜん連絡をよこさない美佐の夫、ボン・ジョビ、ビートルズ、そしてアノ作家の大ベストセラー!
主人公を含めた登場人物たちの言葉も意味深だ。「人間一人の処分代なんて、一〇〇〇円あれば充分なのね」「こんなところに、あんな人がいるんだ」「夫は・・・森へ行ってるんです」「エルメスはどこにやった!」「あんたたち、おかしなことをたくらんでるなら、やめときな」
どれがなんでもないものでどれが物語の真実に迫る鍵か。鍵だったとして、それは「見た目どおり」なのか。絶妙さは湊かなえ先生ならでは。
本書で描かれるのは、人生で一番つらく当たられた人の世話を一手に引き受けていて、しかもまったく感謝されない人たち。その名は、主婦。
悩ましいのは、自由になる手段があり、ノーというべき時が来ても、彼女たちは無用になったものや苦しみを後生大事に抱え込み手放さない。なぜなら、「じゃあ今までのがんばりは何だったのか」と己の積み上げた時間を否定することになるからだ。憎い相手以上に、自分自身への敗北宣言――それは出来ない。登場する女たちが、弱くてみじめでよよよ、と泣くタイプではなく、負けず嫌いぞろいであるのが読みどころ。
そして湊先生の「ヨメ姑もの」(!)でよくあるように、本書でも男たちはある意味アッパレなくらい、ほーんとなんにもしない。ある一つを除いては。
というわけで巷にあふれる鬼の姑、地獄の家庭生活的作品とは一線を画す。義母からのねちねちした嫌味をねちねち描かれたら不快で本をブン投げたくなるが、湊先生は場面や状況を短文で活写する。だから読み味としてはキレよく突き抜けた感じで、言われた側のやるせなさ、くやしさは存分に伝わる。もうサイコー。
上と下、赤と緑、過去と今、他人の家と我が家が複雑に絡み合う、あらたなる湊マジック!

代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ
間 室 道 子
【プロフィール】
ラジオ、TVなどさまざまなメディアで本をおススメする「元祖カリスマ書店員」。雑誌『Precious』、『Fino』に連載を持つ。書評家としても活動中で、文庫解説に『蒼ざめた馬』(アガサ・クリスティー/ハヤカワクリスティー文庫)、『母性』(湊かなえ/新潮文庫)、『蛇行する月』(桜木紫乃/双葉文庫)、『スタフ staph』(道尾秀介/文春文庫)などがある。