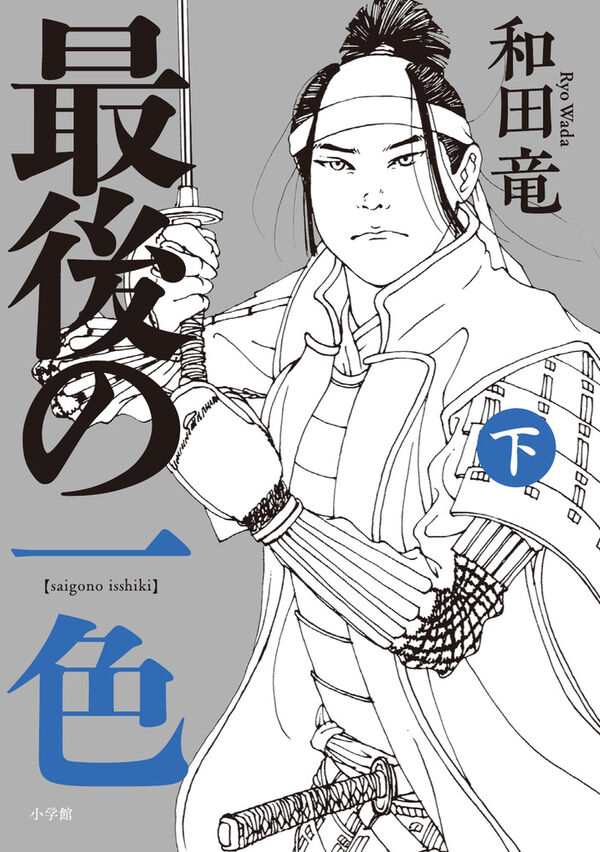【第348回】間室道子の本棚 『最後の一色』和田竜/小学館
「元祖カリスマ書店員」として知られ、雑誌やTVなどさまざまなメディアで本をおススメする、代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ・間室道子。
本連載では、当店きっての人気コンシェルジュである彼女の、頭の中にある"本棚"を覗きます。
本人のコメントと共にお楽しみください。
* * * * * * * *
『最後の一色 上・下』
和田竜/小学館
※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。
※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。
* * * * * * * *
スペクタクルな活劇小説には「ぜひ映像化を」という多くの声が起きる。でも私の考えでは、『最後の一色』は、それなしでも充分イケる。文字でしか得られない脳内での画の結び方がすごいのだ。作者・和田竜さんはカメラのズームや引き、アングルの切り替えをすごく意識して書いていると思う。
たとえば夜、曲がりくねる山道に松明の行列があらわれ、蛇みたいに見えた、というシーン。そのあと炎のひとつに異変が起きる。その小さな異常がなんなのかがわかるとき、ひとりの男が登場する。
軍行のうねりと不気味さと明かりの意味することと男の速度、その書きっぷり。また、伊賀殿というへんな人が天橋立で、ある訓練をしている。彼の呼吸、足どり、次から次へのアクション、口から漏れる怪鳥音!
こういうのは映画化され「正解」として1コの場面を見せられるより文章で味わったほうがぜいたくだと思う。
その時にないものを形容で使うのは反則かもしれぬが、本書はさながら「ジェットコースター歴史時代小説」。そしてジェットコースターは途中で降りられないけど和田さんの文章があまりにはげしく、本書は休み休み読まないとこちらの身がもたない。
ずーっと血沸き肉踊ってるかんじ。一同がおすわりして話し合う会議の場面にも物語のひと休み感はなく、「えっ、そんな案!?」の連続。ふり幅も大きい。緊迫の直後に爆笑し、おそろしさにふるえおののいた次の瞬間拍手喝采の事態に。わたしの情緒はどうにかなりそうだった。
そして本作は「書いて残る」の本質に迫っていると思う。
たとえば、早田道鬼斎(どうきさい)という男。この人は自陣に一大事を告げるため一日で百二十キロを駆け抜けた。当然馬だよな、と思ったのだがどうも脚力オンリーらしい。騎馬では入れぬ山を抜け谷をわたり、最短距離を目指したのだろう。で、彼はその大事件を話し合う場にはおらず、地の文に「歴史上の役目を終える」とあった。
わたしたまげましたわ。「報告したあと過労でばったり倒れて死んだ」とかではないの。この人にはこのあとも人生があったはず。でも「役目を終えた」――なぜなら、そのあとお家の文献にでてこないからである。
もうひとつ、おお、と思ったことがある。早田道鬼斎が知らせた事件について、京都のお坊さんが二種類の日記を書いているのだ。ことを起こした人物にすり寄っている旧版と、うちはそっけない態度をとりました、という新版。
面白いのは、坊さんが両方取っておいたこと。通常は都合がわるいほうはとっとと捨てるだろう。でも、今でこそ事変の結末は確定してるが、今日の優勢が明日に劣勢となりそれが再度ひっくり返るのが戦国。坊さんは「いつかもう一波乱」を見ていたのかもしれない。
どんな劇的な人でも事でも、記されねば、記されても破棄されれば、そこでおしまい。「書き残す」の真髄がここにある。シビれましたねー。
閑話休題、いまさらだが、本書は一色五郎、そして長岡忠興(ただおき)、二人の青年の十七歳から数年間の激突のドラマである。
みなさま、織田信長や明智光秀、秀吉、家康などはご存じ。でも「長岡、一色というお家を知っていますか」「五郎と忠興、ザ・ラスト・スタンディングマンはどちらですか」と言われても、地元周辺や歴史好き以外はポッカーンだろう。それでいいの。二人の熱すぎる戦いにわくわくしよう。
もちろん先ほど「もう一波乱」と書いたが、「信長側だからこっちが」という単純さはない。そして、知ってるでしょ的に有名武将の名前をあげたが、本書には、誰も見たことのない信長や光秀が登場。乞うご期待。
さいごに、和田さんが描きたかったのは「勝つとはなにか」だったのではないかと思う。下巻のラストには生き残ったほうのその後が綴られている。苛烈な人生が続くのだけど書かれ方はたんたんとしていて、私の考えでは、彼は精彩を欠いている。歴史上、出世はしたよ!権力や武力だけじゃない力も発揮したらしいよ!でも、本書に漂う勝者の不思議な虚無を、ご堪能ください。
史実を変えることはできないけど、人が生きたあらわしかたはいくらでも変えることができる。それが作家・和田竜。そして気づいた。作戦を立て、仕掛けをちりばめ、持ち駒の性格、動きを掌握し、放ち、何十万もの読者をノックアウトする。本書の執筆は和田さんにとって、「合戦」なのだ。
たとえば夜、曲がりくねる山道に松明の行列があらわれ、蛇みたいに見えた、というシーン。そのあと炎のひとつに異変が起きる。その小さな異常がなんなのかがわかるとき、ひとりの男が登場する。
軍行のうねりと不気味さと明かりの意味することと男の速度、その書きっぷり。また、伊賀殿というへんな人が天橋立で、ある訓練をしている。彼の呼吸、足どり、次から次へのアクション、口から漏れる怪鳥音!
こういうのは映画化され「正解」として1コの場面を見せられるより文章で味わったほうがぜいたくだと思う。
その時にないものを形容で使うのは反則かもしれぬが、本書はさながら「ジェットコースター歴史時代小説」。そしてジェットコースターは途中で降りられないけど和田さんの文章があまりにはげしく、本書は休み休み読まないとこちらの身がもたない。
ずーっと血沸き肉踊ってるかんじ。一同がおすわりして話し合う会議の場面にも物語のひと休み感はなく、「えっ、そんな案!?」の連続。ふり幅も大きい。緊迫の直後に爆笑し、おそろしさにふるえおののいた次の瞬間拍手喝采の事態に。わたしの情緒はどうにかなりそうだった。
そして本作は「書いて残る」の本質に迫っていると思う。
たとえば、早田道鬼斎(どうきさい)という男。この人は自陣に一大事を告げるため一日で百二十キロを駆け抜けた。当然馬だよな、と思ったのだがどうも脚力オンリーらしい。騎馬では入れぬ山を抜け谷をわたり、最短距離を目指したのだろう。で、彼はその大事件を話し合う場にはおらず、地の文に「歴史上の役目を終える」とあった。
わたしたまげましたわ。「報告したあと過労でばったり倒れて死んだ」とかではないの。この人にはこのあとも人生があったはず。でも「役目を終えた」――なぜなら、そのあとお家の文献にでてこないからである。
もうひとつ、おお、と思ったことがある。早田道鬼斎が知らせた事件について、京都のお坊さんが二種類の日記を書いているのだ。ことを起こした人物にすり寄っている旧版と、うちはそっけない態度をとりました、という新版。
面白いのは、坊さんが両方取っておいたこと。通常は都合がわるいほうはとっとと捨てるだろう。でも、今でこそ事変の結末は確定してるが、今日の優勢が明日に劣勢となりそれが再度ひっくり返るのが戦国。坊さんは「いつかもう一波乱」を見ていたのかもしれない。
どんな劇的な人でも事でも、記されねば、記されても破棄されれば、そこでおしまい。「書き残す」の真髄がここにある。シビれましたねー。
閑話休題、いまさらだが、本書は一色五郎、そして長岡忠興(ただおき)、二人の青年の十七歳から数年間の激突のドラマである。
みなさま、織田信長や明智光秀、秀吉、家康などはご存じ。でも「長岡、一色というお家を知っていますか」「五郎と忠興、ザ・ラスト・スタンディングマンはどちらですか」と言われても、地元周辺や歴史好き以外はポッカーンだろう。それでいいの。二人の熱すぎる戦いにわくわくしよう。
もちろん先ほど「もう一波乱」と書いたが、「信長側だからこっちが」という単純さはない。そして、知ってるでしょ的に有名武将の名前をあげたが、本書には、誰も見たことのない信長や光秀が登場。乞うご期待。
さいごに、和田さんが描きたかったのは「勝つとはなにか」だったのではないかと思う。下巻のラストには生き残ったほうのその後が綴られている。苛烈な人生が続くのだけど書かれ方はたんたんとしていて、私の考えでは、彼は精彩を欠いている。歴史上、出世はしたよ!権力や武力だけじゃない力も発揮したらしいよ!でも、本書に漂う勝者の不思議な虚無を、ご堪能ください。
史実を変えることはできないけど、人が生きたあらわしかたはいくらでも変えることができる。それが作家・和田竜。そして気づいた。作戦を立て、仕掛けをちりばめ、持ち駒の性格、動きを掌握し、放ち、何十万もの読者をノックアウトする。本書の執筆は和田さんにとって、「合戦」なのだ。

代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ
間 室 道 子
【プロフィール】
ラジオ、TVなどさまざまなメディアで本をおススメする「元祖カリスマ書店員」。雑誌『Precious』に連載を持つ。書評家としても活動中で、文庫解説に『蒼ざめた馬』(アガサ・クリスティー/ハヤカワクリスティー文庫)、『母性』(湊かなえ/新潮文庫)、『蛇行する月』(桜木紫乃/双葉文庫)、『スタフ staph』(道尾秀介/文春文庫) 、『プルースト効果の実験と結果』(佐々木愛/文春文庫)などがある。