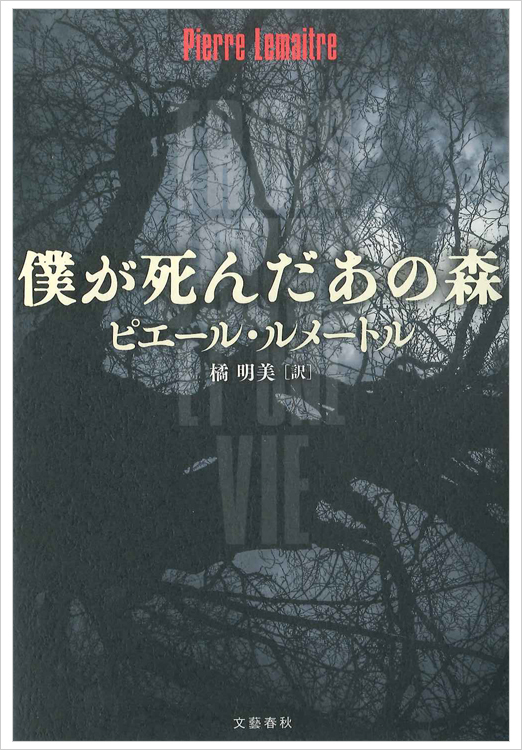【第146回】間室道子の本棚 『僕が死んだあの森』ピエール・ルメートル 橘明美訳/文藝春秋
「元祖カリスマ書店員」として知られ、雑誌やTVなどさまざまなメディアで本をおススメする、代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ・間室道子。
本連載では、当店きっての人気コンシェルジュである彼女の、頭の中にある"本棚"を覗きます。
本人のコメントと共にお楽しみください。
* * * * * * * *
『僕が死んだあの森』
ピエール・ルメートル 橘明美訳/文藝春秋
※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。
※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。
* * * * * * * *
『その女アレックス』や『傷だらけのカミーユ』がヒットした著者の最新刊。題に女性名がつくこれらシリーズの凄惨なシーンにうげげ、となり、以来この人の作品NGな方、本書には過剰な暴力は出てこないです。そしてすごく面白いですよ!
舞台はクリスマスシーズンのフランスの小さな村で、主人公は十二歳の少年アントワーヌ。性に目覚める年齢であり、思春期男子特有の自意識過剰で毎日キーッとなりがち。
で、まず「女の子の件」があり、続いて「犬の件」があった。カーッとした彼は、森の中で隣家の六歳の男の子レミを殺してしまうのである。三日間の悪夢が始まる。
自分を慕ってくれた子だったのに!と涙にくれながら、頭のいい彼の脳裏には「子供を殺した大人の末路も悲惨だが、子供を殺した子供はどうなるか」がよぎる。そして彼の家は母ひとり子ひとり。このお母さんが凡庸に見えてなかなかエキセントリックで、自分の評判に傷がつくことをなによりも恐れている。アントワーヌの人生の目標は「母が後ろ指をさされないようにする」なのだ。というわけで死体を隠した。その後、「幼いレミがいない」が広まるにつれ、村は「迷子?」「誘拐?」「もしかして変態出現?」と大騒ぎに。
殺人者を主人公にした話はいろいろあり、読者は「早くつかまればいいのに!」か「逃げおおせてくれたら!」と思いながら読み進む。でも本書はどちらでもない。主人公に降りかかるとてつもない恐怖を読者もひたすら味わうことになる。なぜなら、犯人が子供だからだ。
アントワーヌはさまざまな妄想をし、震え上がる。たとえば「バレてレミのお父さんがいきなり僕を銃で撃つ」とか「憲兵隊の隊長さんが千里眼」とか。それはないって!と突っ込みたくなるけど、でも子供って、何も悪いことをしていなくても大人が怖いものだ。いわんや人殺しとなったこの子をや!
また、逃げようにもお金が一人でおろせないし、どこにいったらいいかもわからない。「逃亡先として有名なのはオーストラリアとか南米だけど、マルセイユから行けるのかしら」と考えるシーンは、滑稽で、あわれで、涙が出ちゃう。
有利なこともある。やってきた憲兵たちを見て大人が顔面蒼白になったり泣き出したりしたら「こいつ、怪しい」となるだろう。でも子供の場合は「緊張してるんだね」「怖がらなくていいんだよ」「仲のよい子がいなくなったんだ、ショックを受けてるんだろう」と勝手に解釈してくれるのである!
さて、この手の事件があると、日常の奥底が浮上するものだ。ここ数年、村長が経営している木製玩具工場が不況でどんどん人を削減。六歳児失踪を機に、村のリーダー兼雇用主への、皆の不安、不満、不信が沸騰。
で、著者ルメートルはよきところでお話をジャンプさせるのが得意。読者が「え、そっち行きます?!」とびっくりする展開になっていくのだ。本書でも「男の子の行方不明事件にかまっちゃいられない事態」が起きるのである!
そしてお話の三分の二あたりで舞台は十二年後に。アントワーヌはどうなったか。そしてまたもやジャンプ発動!「あ、そういう話!?」と読者は口をあんぐりであろう。さらにラストシーン。最後の大跳躍に「そうだったのかー」と放心状態必至。
原題は『Trois jours et une vie』で直訳すると「三日間、そしてひとつの人生」なのだけど、読後、誰もが邦題の素晴らしさにシビれるだろう。訳の橘明美さん&編集さんに大拍手。
舞台はクリスマスシーズンのフランスの小さな村で、主人公は十二歳の少年アントワーヌ。性に目覚める年齢であり、思春期男子特有の自意識過剰で毎日キーッとなりがち。
で、まず「女の子の件」があり、続いて「犬の件」があった。カーッとした彼は、森の中で隣家の六歳の男の子レミを殺してしまうのである。三日間の悪夢が始まる。
自分を慕ってくれた子だったのに!と涙にくれながら、頭のいい彼の脳裏には「子供を殺した大人の末路も悲惨だが、子供を殺した子供はどうなるか」がよぎる。そして彼の家は母ひとり子ひとり。このお母さんが凡庸に見えてなかなかエキセントリックで、自分の評判に傷がつくことをなによりも恐れている。アントワーヌの人生の目標は「母が後ろ指をさされないようにする」なのだ。というわけで死体を隠した。その後、「幼いレミがいない」が広まるにつれ、村は「迷子?」「誘拐?」「もしかして変態出現?」と大騒ぎに。
殺人者を主人公にした話はいろいろあり、読者は「早くつかまればいいのに!」か「逃げおおせてくれたら!」と思いながら読み進む。でも本書はどちらでもない。主人公に降りかかるとてつもない恐怖を読者もひたすら味わうことになる。なぜなら、犯人が子供だからだ。
アントワーヌはさまざまな妄想をし、震え上がる。たとえば「バレてレミのお父さんがいきなり僕を銃で撃つ」とか「憲兵隊の隊長さんが千里眼」とか。それはないって!と突っ込みたくなるけど、でも子供って、何も悪いことをしていなくても大人が怖いものだ。いわんや人殺しとなったこの子をや!
また、逃げようにもお金が一人でおろせないし、どこにいったらいいかもわからない。「逃亡先として有名なのはオーストラリアとか南米だけど、マルセイユから行けるのかしら」と考えるシーンは、滑稽で、あわれで、涙が出ちゃう。
有利なこともある。やってきた憲兵たちを見て大人が顔面蒼白になったり泣き出したりしたら「こいつ、怪しい」となるだろう。でも子供の場合は「緊張してるんだね」「怖がらなくていいんだよ」「仲のよい子がいなくなったんだ、ショックを受けてるんだろう」と勝手に解釈してくれるのである!
さて、この手の事件があると、日常の奥底が浮上するものだ。ここ数年、村長が経営している木製玩具工場が不況でどんどん人を削減。六歳児失踪を機に、村のリーダー兼雇用主への、皆の不安、不満、不信が沸騰。
で、著者ルメートルはよきところでお話をジャンプさせるのが得意。読者が「え、そっち行きます?!」とびっくりする展開になっていくのだ。本書でも「男の子の行方不明事件にかまっちゃいられない事態」が起きるのである!
そしてお話の三分の二あたりで舞台は十二年後に。アントワーヌはどうなったか。そしてまたもやジャンプ発動!「あ、そういう話!?」と読者は口をあんぐりであろう。さらにラストシーン。最後の大跳躍に「そうだったのかー」と放心状態必至。
原題は『Trois jours et une vie』で直訳すると「三日間、そしてひとつの人生」なのだけど、読後、誰もが邦題の素晴らしさにシビれるだろう。訳の橘明美さん&編集さんに大拍手。