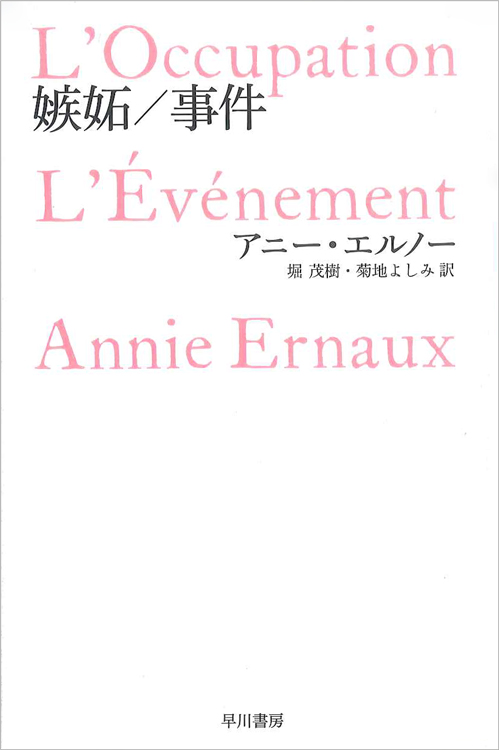【第218回】間室道子の本棚 『嫉妬/事件』アニー・エルノー 堀茂樹・菊地よしみ訳/ハヤカワepi文庫
「元祖カリスマ書店員」として知られ、雑誌やTVなどさまざまなメディアで本をおススメする、代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ・間室道子。
本連載では、当店きっての人気コンシェルジュである彼女の、頭の中にある"本棚"を覗きます。
本人のコメントと共にお楽しみください。
* * * * * * * *
『嫉妬/事件』
アニー・エルノー 堀茂樹・菊地よしみ訳/ハヤカワepi文庫
※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。
※画像をクリックすると購入ページへ遷移します。
* * * * * * * *
2022年のノーベル文学賞作家アニー・エルノーは、自身に起きたことを活写し、読ませていく作家だ。”誰か”ではなく”私のはなし”。本書には映画化で話題の「事件」も併録されているけど「嫉妬」がめちゃくちゃ面白かった。
別れを切り出したのは自分のほうだった。でも二、三カ月後、男が別な女性と暮らしはじめると知って「私」はいてもたってもいられなくなる。「それはどんな女なの?」にとりつかれるのだ。できごと、考え、感情が詳細に綴られていく。
なんとしてでも、彼女の姓名を、年齢を、職業を、住所を、知りたい――。
別れたあとも、「私」は男に電話していたし会ってもいた。彼はしぶしぶ、彼女は四十七歳で、教師であり、離婚歴があって十六歳の娘がいる、パリ七区のラップ大通りに住んでいる、と洩らす。
男は三十代で、新恋人が彼と同世代あるいは年下だったならご破算にした関係はそのうち忘却の彼方、消滅となっただろう。でも自分と同じ、熟年女性――。嫉妬は沸点に達する。最初に書いたように、終わりを告げたのは「私」のほうだ。でもこの展開で、「彼らのあたらしい恋愛」は「自分が叶えられなかったこと」になったのである。
よく「いらなくなったおもちゃでも誰かの手に渡ると惜しくなる」というけど、本書にでてくるのはそういう安易さではない。もちろん、「彼をもう一度自分のものにしたかった」という一行もある。しかし、もし男がきみのそばに戻ると言ったならその一分後、自分が何を思うかも、冷徹に、気だるげに、書き留められている。
読みどころは「私」が彼より「その女」に執着していくことだ。
赤裸々に文章化される、異様な行動と妄想。「やりすぎだ」と「あるある」の間で読者は揺れるだろう。どの部分に共感しどこにあきれたかで読み手の今までの恋愛体験がバクロされそうだが、わたしがもっとも「わかる!」と思ったのは、「47」への敏感性だ。
彼女の年齢だという数字に過ぎないのに、4と7の並びに目ざとくなる。47が自分を狙って行く先々に突っ立っているぐらいに思ってしまうのだ。
常軌を逸しているとわかっていても、世界に、一度もあったことのない人の存在ばかりを見てしまう。相手についてより深い情報を得たと思った時の、達成感、幸福、有頂天。誰もが、まるで恋してるみたいだ、と思うだろう。
そう、狂おしいほど相手を思うという点では、嫉妬は盲目的な愛と似ているのかもしれない。いや、でも本書の世界はそんなに単純ではない。幾重もの心のひだと、複雑性。
知ってどうする、ということに熱量を注ぎ、得て何になる、というものに手を伸ばし続ける。アニー・エルノーは「嫉妬の物語」ではなく、「嫉妬」そのものを文学に焼き付けることに成功した。
別れを切り出したのは自分のほうだった。でも二、三カ月後、男が別な女性と暮らしはじめると知って「私」はいてもたってもいられなくなる。「それはどんな女なの?」にとりつかれるのだ。できごと、考え、感情が詳細に綴られていく。
なんとしてでも、彼女の姓名を、年齢を、職業を、住所を、知りたい――。
別れたあとも、「私」は男に電話していたし会ってもいた。彼はしぶしぶ、彼女は四十七歳で、教師であり、離婚歴があって十六歳の娘がいる、パリ七区のラップ大通りに住んでいる、と洩らす。
男は三十代で、新恋人が彼と同世代あるいは年下だったならご破算にした関係はそのうち忘却の彼方、消滅となっただろう。でも自分と同じ、熟年女性――。嫉妬は沸点に達する。最初に書いたように、終わりを告げたのは「私」のほうだ。でもこの展開で、「彼らのあたらしい恋愛」は「自分が叶えられなかったこと」になったのである。
よく「いらなくなったおもちゃでも誰かの手に渡ると惜しくなる」というけど、本書にでてくるのはそういう安易さではない。もちろん、「彼をもう一度自分のものにしたかった」という一行もある。しかし、もし男がきみのそばに戻ると言ったならその一分後、自分が何を思うかも、冷徹に、気だるげに、書き留められている。
読みどころは「私」が彼より「その女」に執着していくことだ。
赤裸々に文章化される、異様な行動と妄想。「やりすぎだ」と「あるある」の間で読者は揺れるだろう。どの部分に共感しどこにあきれたかで読み手の今までの恋愛体験がバクロされそうだが、わたしがもっとも「わかる!」と思ったのは、「47」への敏感性だ。
彼女の年齢だという数字に過ぎないのに、4と7の並びに目ざとくなる。47が自分を狙って行く先々に突っ立っているぐらいに思ってしまうのだ。
常軌を逸しているとわかっていても、世界に、一度もあったことのない人の存在ばかりを見てしまう。相手についてより深い情報を得たと思った時の、達成感、幸福、有頂天。誰もが、まるで恋してるみたいだ、と思うだろう。
そう、狂おしいほど相手を思うという点では、嫉妬は盲目的な愛と似ているのかもしれない。いや、でも本書の世界はそんなに単純ではない。幾重もの心のひだと、複雑性。
知ってどうする、ということに熱量を注ぎ、得て何になる、というものに手を伸ばし続ける。アニー・エルノーは「嫉妬の物語」ではなく、「嫉妬」そのものを文学に焼き付けることに成功した。

代官山 蔦屋書店 文学担当コンシェルジュ
間 室 道 子
【プロフィール】
雑誌やTVなどさまざまなメディアで本をおススメする「元祖カリスマ書店員」。雑誌『婦人画報』、朝日新聞デジタル「ほんやのほん」などに連載を持つ。書評家としても活動中で、文庫解説に『蒼ざめた馬』(アガサ・クリスティー/ハヤカワクリスティー文庫)、『母性』(湊かなえ/新潮文庫)、『蛇行する月』(桜木紫乃/双葉文庫)、『スタフ staph』(道尾秀介/文春文庫)などがある。