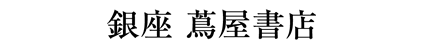【特別対談|土屋秋恆×吉田山】伝統芸術を起点に日本の輪郭をアクチュアルに引き直す表現者たちの挑戦
蔦屋書店の中ではアートギャラリーを有する初めての店舗である銀座 蔦屋書店。
ギャラリーや書店内の書架や専用棚で日本と西洋、そして伝統芸術から現代アートの作品や画集を総合的に展開、本を通じてアートと生活を接続して「アートのある暮らし」を提案しています。
今回は近年再評価が進む水墨画に焦点をあて、水墨画家・土屋秋恆氏と数々の展覧会などのディレクターで知られる吉田山氏をお迎えしました。
ギャラリーや書店内の書架や専用棚で日本と西洋、そして伝統芸術から現代アートの作品や画集を総合的に展開、本を通じてアートと生活を接続して「アートのある暮らし」を提案しています。
今回は近年再評価が進む水墨画に焦点をあて、水墨画家・土屋秋恆氏と数々の展覧会などのディレクターで知られる吉田山氏をお迎えしました。
世界のグローバル化が加速し、疫病、災害、ジェノサイドなど未曾有の危機が続くなか、日本国内をベースにトランスナショナルな視座をもって越境する表現者たちはいま何を見ているのか。
若干18歳で水墨画家の寺山南楊をもって「大家の相がある」と言わしめた高度な古典技法を持ちながら、後期具体を代表する作家である松田豊に師事した土屋秋恆。そして「同路上性」を掲げたアートスペースの企画運営や、さまざまなアートフェスや展覧会のディレクションや作品制作など縦横無尽な活躍で注目を集める吉田山。
8月19日から京都・両足院での個展を控えた土屋秋恆の「脳内之万象」新作シリーズを囲み、歴史と伝統を継承すると同時に形式を問い脱構築する反復の中で、新たな視覚体験を切り拓く試みについて話を聞いた。(聞き手・執筆:鈴木沓子、写真:田口るり子)
ーー来月両足院で展示される作品と同じシリーズの本作「脳内之万象 神宮前」でも描かれていますが、髑髏は長年のモチーフだそうですね。
土屋:髑髏を描き始めたのは2006年からでした。友人から墨で描いた髑髏が見てみたいと言われて、実際に描き始めて気付いたんです。頭蓋骨は人類の生命と叡智の象徴であり、全人類ほぼ同じ形をしている普遍的かつ象徴的な存在で、かのアインシュタインは「すべての宗教、芸術、科学は、同じ一つの樹の枝である」という言葉を残しました。つまり人類は頭蓋骨の元に平等であり、大都会で暮らしていてもジャングルで暮らしていても、日照時間の変化や月の満ち欠けという自然や、宇宙のサイクルの影響から逃れられない。人間の脳神経は樹木のように張り巡らされ、自然や宇宙の一部なんだというイメージを髑髏を使って視覚化しました。
また人間の視覚から脳内に入った情報は時間と共に記憶として無くなってしまっても、実はその記憶や経験は湖の水のように溜まって、存在し続けるような気がしているんです。それが干上がったり無くなったように見えても、それは雲として上空にクラウドのように上がっていて、やがて雨として降り注いで、森を通る川となって湖に戻りまた循環する。自然と人、宇宙全体と人間の脳内は同じ構造ではないかという発想で自分の脳内活動を視覚化してみたのですが、脳神経外科の医師に「実際の脳の構造とほぼ同じ形になっている」と驚かれたことがあります。脳下垂体や海馬の位置が同じだ、と。
また人間の視覚から脳内に入った情報は時間と共に記憶として無くなってしまっても、実はその記憶や経験は湖の水のように溜まって、存在し続けるような気がしているんです。それが干上がったり無くなったように見えても、それは雲として上空にクラウドのように上がっていて、やがて雨として降り注いで、森を通る川となって湖に戻りまた循環する。自然と人、宇宙全体と人間の脳内は同じ構造ではないかという発想で自分の脳内活動を視覚化してみたのですが、脳神経外科の医師に「実際の脳の構造とほぼ同じ形になっている」と驚かれたことがあります。脳下垂体や海馬の位置が同じだ、と。
吉田山:面白いですね。メキシコなんかだと、髑髏は前向きな死生観のモチーフだし、むしろ「死者の象徴」として考えられるけど、そうではない。うろ覚えですが、視覚情報のある角度から外角も、脳内で色彩の情報を処理して認識していると聞いたことがあります。目で捉えているリアルタイムの情報はある程度の時点ではモノクロらしいですね。

京都・両足院で開催予定(8月19〜25日)の土屋秋恆 水墨画展「脳内之万象 京都」より
土屋:それは実感としてわかります。例えば、バイクに乗っている時、スピードを上げれば上げるほど、視界の範囲が狭くなる。体感的には目の前の50cm幅程だけがちゃんと見えている感覚です。そのほかの範囲は実際は目に見えているのかもしれませんが、情報処理が追い付かなくて飛ばしている。別の例を挙げると、壁の汚れやシミの模様が、何か別のものに見えてくることがありますよね。水墨画で「見立て」と言いますが、無秩序な墨の滲みや溜まり、ガサガサと筆が紙の上でのたうち回っているような、いわゆる汚れのような模様を作って、木や岩に見立てて描き進むことで、正確に写生するよりも勢いのある生き生きとした描写にすることができる。正しく描こうとするよりも、その本質を捉えようとしてるんです。人間の目は高性能ですが、雑な部分もある。日常的に目で見えていると思っている景色も、実は見えていなくて脳が想像で補足している部分もかなりあります。
吉田山:僕はビジュアルアートや展覧会を作る仕事をしていますので、「見る」をつくる仕事をしているとも言えます。たとえば展覧会という受け皿を作って、作品を配置して、光を当てたり、反射させて、どうやって見せていこうかと試行錯誤しているのですが、決してコントロールできるものではないはないし、でも常に本質を捉えたいと思っていますので、近いものを感じます。

ーー光の反射は色彩の認知に欠かせない要素ですよね。墨で森羅万象を表現する水墨画では、濃淡を調整する技術が、光と色彩の表現を担っている部分もあるのでしょうか。
土屋:そもそも水墨画の起源は仏画で白描画と言うんですが、要は線で仏様の輪郭を描いただけのものだったんです。それからだんだん墨の濃淡を使った水墨画になっていくのですが、濃淡と言っても墨の中には茶色く見える墨と、青く見える墨が2種類あります。例えば、青みの強い青墨(せいぼく)を使って海の景色を描くと、寒々しく荒々しい日本海のように見えるし、茶色みの強い茶墨(ちゃぼく)を使って木々や森を描くと、生き生きと育つ夏の森のように見えるんです。要は墨の中にほんの少し見える「色み」によって脳内が温度感を想像して補足している訳です。
吉田山:私は富山市出身で、近所に水墨画美術館があって幼い頃に遠足で行っていたのですが、それ以降はあまり触れてきたことがなかったんです。なので、素朴な感想ですが、墨にも色味の違いがはっきりあることに驚いていますし、たしかにモノクロームでも実際に色合いが見えてきます。これは今までの記憶を思い出している部分もあるだろうし、人生経験によって見える色合いや情緒も違うのではと思いました。かなり昔、数世紀前から少しずつ変化して今、土屋さんがおこなっている現代的な水墨画がどのようなものかも気になっています。

ーー水墨画を学びながら、具体美術協会の最年少作家である松田豊さんに師事されたり仏像彫刻を学ばれたのは、当時どのような経緯があったのでしょうか。
土屋:水墨画家になろうと決めた21歳からの数年間は五里霧中で最も辛い時期でした。自分がどんなに高い志を持って水墨画を世の中に広めたいと言っても、経験値も知名度もゼロで、まだ何者でもない。水墨画家として色々と試行錯誤する中、芸術家としてもっと幅広い感性を学ばなければと思っていた時に、知人から具体美術協会の松田豊先生を紹介されました。松田先生は僕の芸術に対する固定概念を取り払ってくださいました。そして先生からアートに対する考え方や姿勢などの多くを学びました。僕から見た松田先生の作品には、混沌とした中にも美しい秩序があるように思いました。たとえ無意識であっても、画角上の構図が、いつもものすごく緻密に計算されてると。
吉田山:ものすごくざっくりと言いますが、松田豊さんの所属していたGUTAIは日本人が持っている奥ゆかしい感性や形式、水墨画の態度のようなものを破壊して西洋化しようという運動ですよね。その相反すると思われるものを同時に学んだことはとても気になります。
土屋:そうですね。でも松田先生が作るキネティックアートにも、すごく日本人的で繊細な奥ゆかしさの美学があると感じていました。文化に根付いた様式美は、そう簡単に捨てられるものではないのかもしれないと思いました。そして僕自身は水墨画と具体の現代アートを同時に学ぶ中で、精神を解放し過ぎてしまった結果、ある日、急に頭が混乱して、言語がおかしくなってしまった時期があったんです。言葉ではない世界に没入してしまったというか。そこである種救いを求めるように、仏師の水戸川櫻華先生に師事して仏像を彫りだしました。何体か彫ったある日、聖観音菩薩を彫っている途中に急に何か心が救われたような、視界が開けたような気がして、その彫りかけの聖観音菩薩は彫りかけのままで今も置いてあるんです。
吉田山:『火の鳥』の「鳳凰編」のような話ですね。話の筋は異なりますが、とある男が一心不乱に仏像を彫り、どのような状況でも制作を続けることで次第に救われていくという…。
土屋:感覚的には苦しかったですが、今振り返るとクリエイティブでとても大切な時間でした。白髪一雄先生にも水墨画は続けなさいって励ましてもらいましたね。水墨画は揮毫や席画といって人前で描くことも多いので、アクションペインティングとして見てくださっていたのかもしれません。

吉田山:例えば、アメリカンポップアートやニューペインティングは、近くで見るようなものではないですよね。そもそもアメリカは大陸が広大な国。だから侘び寂びより、作品から遠く離れた場所からも見えたほうがいい、大きいことがいいと、横へ横へと伸びていく。バイクや車もそうですが、人間の身体能力を拡張していくことの正義や世界観がありますよね。
土屋:うちの師匠は「水墨画は日本に入ってきてさらに磨かれた」という言い方をしていました。もちろん中国には中国の良さがありますが、日本独自の発展があったということだと思います。水墨画は日本に入ってきた当時、もともと幕府が自らの権威を示すために宮廷画家である狩野派に絢爛豪華な絵を描かせてきた中で、そうした水墨画とは対照的に、生成りの紙や劣化した素材に美しさを見出したり、枯れの中にある雅を提唱する人たちが登場した。狩野派と長谷川等伯の戦いですね。消え入りそうな等伯の松の絵も最初は批判があったんですよね。でも消え入るような淡い線や、その奥にいろいろなものを見立てることで、想像力をもって能動的に働きかける日本固有の世界観や美学が生まれた。
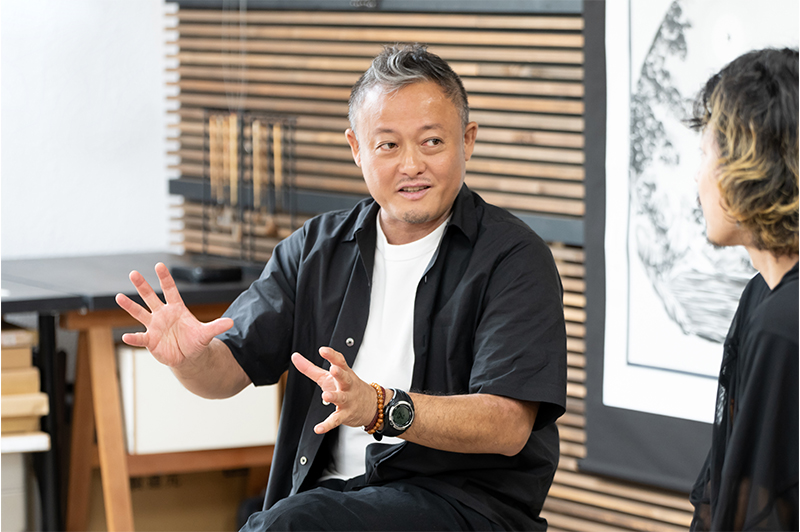
吉田山:僕は学生時代に少し弓道をやっていたのですが、弓道は<当てに行く>のではなくて、「射法八節」という八つの型で体を動かして弓を放しているんです。その型を続けていくと、結果的に弓が的に当たる。かつて(スティーブ)ジョブスも読んでいたという有名な本『弓と禅』では、弟子が師匠に「当てに行くな」とめちゃくちゃ怒られるシーンがあって、そのシーンは今でも覚えています。
土屋:剣道も、居合も、弓道も、基本的に突き詰めると自分との戦い。僕は性別・年齢・国籍、様々な生徒を教えてきましたが、スジが良くあっという間に上手くなる人はラグビーかサッカーをやっていた人が多かった。自分の弟子は2人ともスポーツ経験者です。長く野球をやっていたというアメリカ人の生徒さんもとても呑み込みが早かったですね。彼の話で印象的だったのが「僕たちはまずコーチに対するリスペクトがある、それから言われたとおりに体を動かす癖が習慣になって身に付いてる」と。そもそも体幹がしっかりしているので線が安定しているし、どれも水墨画の素養として重要な要素なんです。
吉田山:先生や師匠ではなく、"コーチ"と呼ばれるんですね(笑)。そうやって言語化されるとはっとさせられますね。
土屋:そこに信頼があるんですよね。僕もコーチと選手の関係をあまりわかってなかったけど、師弟もそういうことだなと思いました。コーチから「その動きではない」と自分がやってきたことを否定されても、一から組み立て直すことができるロジックを持っていることはとても強い。水墨画は描き直しができないので、乾ききる前に一気に描かないといけない。だから思ったところに筆を動かせるかどうかがとても重要。体重移動、体幹の動かし方、腕や肩の回し方、と、ある意味アスリートの感性や身体性が求められる部分がかなりあります。紙と自分の距離や立ち位置やスタンスの取り方で筆致が変わってくる。その点ではストリートアートの人たちとも近いものがあるかもしれません。

吉田山:僕は2018年から2020年、外苑前のビンテージマンションの一室でアートスペースを運営していたのですが、その場所が新国立競技場からすごく近かったので、2021年に延期してしまった東京オリンピックのもともとの開催予定日にあわせて「芸術競技」という展覧会を開催したんです。歴史的に言うと、古代オリンピックが無くなったあと、近代オリンピックを立ちあげるときに近代と古代の違いとして種目が増えたときに、スポーツ以外の美術、芸術で金、銀、銅メダルを競うという「芸術競技」というものがあった。それを展覧会のタイトルに持ってきて、実際に新国立競技場の周りをパフォーマンスしながら巡るイベントや展示をしました。僕自身、スポーツ選手ではなく、別の人たちが二次産物的に手に入れた身体の動きの方に興味があります。
土屋:僕が水墨画を始めた高校生の時はアメカジブームで、その頃ロックやファンクに夢中になってドラムを叩き、ジーンズに革ジャンを着てバイクに乗っていました。未だにハーレーも好きで乗っています。その一方で水墨画は色即是空がテーマで、自分の中には禅に近い思想がある。今年50代に入ることもあって、これまで描いたことがなかった自画像を描いてみようと思っています。そもそも自画像という考え方自体、東洋的ではないのですよね。でも「脳内之万象」のように人間と自然、脳内と宇宙の表裏一体を表す世界観のように、古典も現代も東洋も西洋もミクロもマクロも取り込んで形成してきた自分を見つめ直して、主観と客観のいずれの視点を織り交ぜた自分自身を描くタイミングに来ていると感じています。
[プロフィール]
土屋秋恆(つちや・しゅうこう)
1974年 宝塚生まれ。東京在住。
水墨画家、南北墨画会師範、ステインアーティスト。18歳で水墨画を始め、2年という異例の早さで師範となる。古典的技法への高い技術と現代的な画材やテーマを導入する独自のスタイルで注目を集め、松蔭神社、東霧島神社、深谷薬師瑠璃光寺、等が作品を所蔵するほか、アメリカ、スペイン、インドなど世界各国での展示やブータン国王室への作品寄贈も。クリスチャン・ディオールやフェラーリなど、数々のハイブランドやミュージシャンなど国境とジャンルを越境した創作活動を展開。日本書画展褒章受賞、全国水墨研究会合同展 無鑑査大賞受賞 。
[プロフィール]
土屋秋恆(つちや・しゅうこう)
1974年 宝塚生まれ。東京在住。
水墨画家、南北墨画会師範、ステインアーティスト。18歳で水墨画を始め、2年という異例の早さで師範となる。古典的技法への高い技術と現代的な画材やテーマを導入する独自のスタイルで注目を集め、松蔭神社、東霧島神社、深谷薬師瑠璃光寺、等が作品を所蔵するほか、アメリカ、スペイン、インドなど世界各国での展示やブータン国王室への作品寄贈も。クリスチャン・ディオールやフェラーリなど、数々のハイブランドやミュージシャンなど国境とジャンルを越境した創作活動を展開。日本書画展褒章受賞、全国水墨研究会合同展 無鑑査大賞受賞 。


吉田山(よしだやま)
熱海と東京都内を拠点とするアート・アンプリファイア(増殖器)。
都市と山村の生活経験やその地の歴史を素材とし、都市のインフラや場所をオブジェクトとして再利用する思索を元に展覧会キュレーション/アートプロジェクト実践/出版/経営を試みつつ、社会のオルタナティブな関係性を実践している。
近年の主なプロジェクトに『都市GENEの抽出・反転・流通』(BankART Station,横浜,2024)、『俯いて見る/Gaze this urbs with downcast eyes.(APRDELESP,CDMX,2024)、『MALOU A-F』(やんばるアートフェスティバル,沖縄,2024)、キュレーターとして『URBAN GAZE』(APRDELESP,CDMX,2024)、『AUGMENTED SITUATION D』(CCBT 渋谷駅周辺,東京,2023)『風の目たち』(ジョージア&トルコ,2022-)、『のけもの』(アーツ千代田3331屋上,東京,2021)、『インストールメンツ』 (投函形式,住所不定,2020)等。
熱海と東京都内を拠点とするアート・アンプリファイア(増殖器)。
都市と山村の生活経験やその地の歴史を素材とし、都市のインフラや場所をオブジェクトとして再利用する思索を元に展覧会キュレーション/アートプロジェクト実践/出版/経営を試みつつ、社会のオルタナティブな関係性を実践している。
近年の主なプロジェクトに『都市GENEの抽出・反転・流通』(BankART Station,横浜,2024)、『俯いて見る/Gaze this urbs with downcast eyes.(APRDELESP,CDMX,2024)、『MALOU A-F』(やんばるアートフェスティバル,沖縄,2024)、キュレーターとして『URBAN GAZE』(APRDELESP,CDMX,2024)、『AUGMENTED SITUATION D』(CCBT 渋谷駅周辺,東京,2023)『風の目たち』(ジョージア&トルコ,2022-)、『のけもの』(アーツ千代田3331屋上,東京,2021)、『インストールメンツ』 (投函形式,住所不定,2020)等。